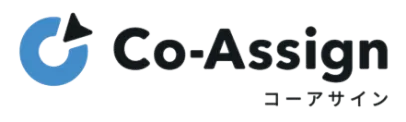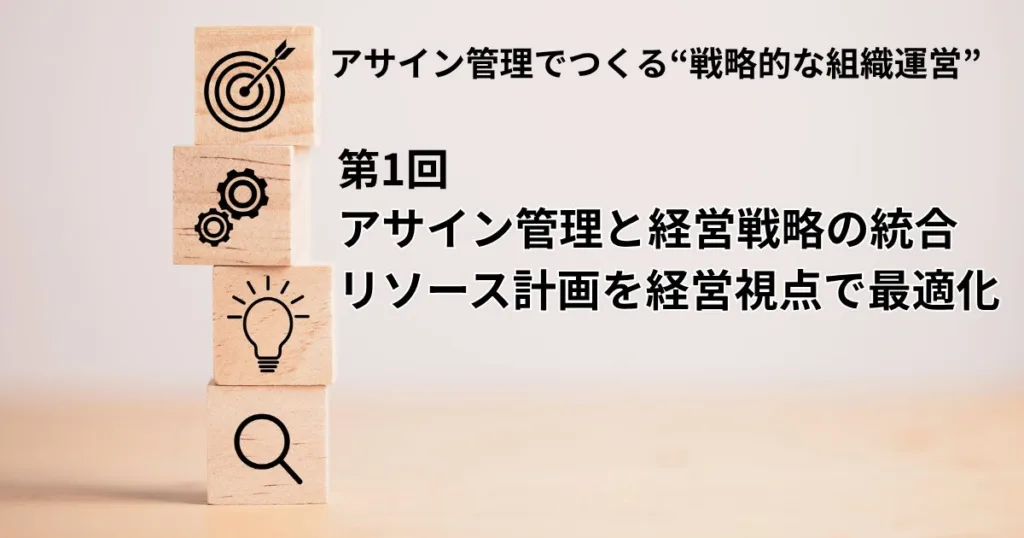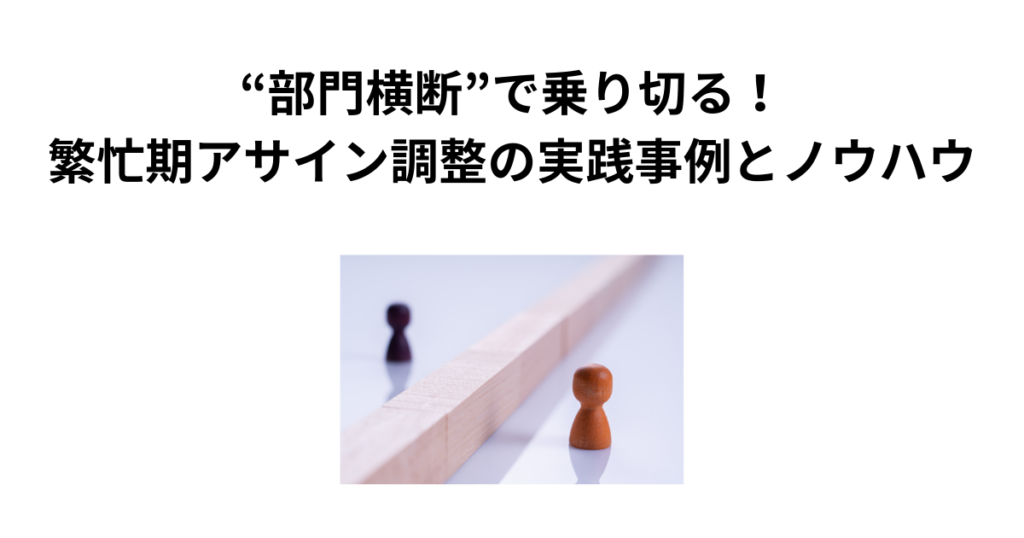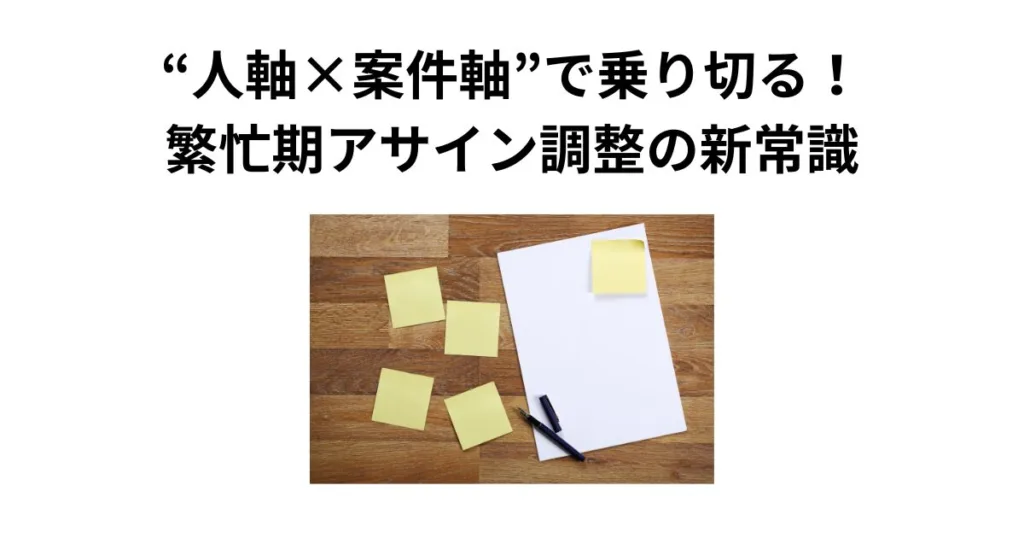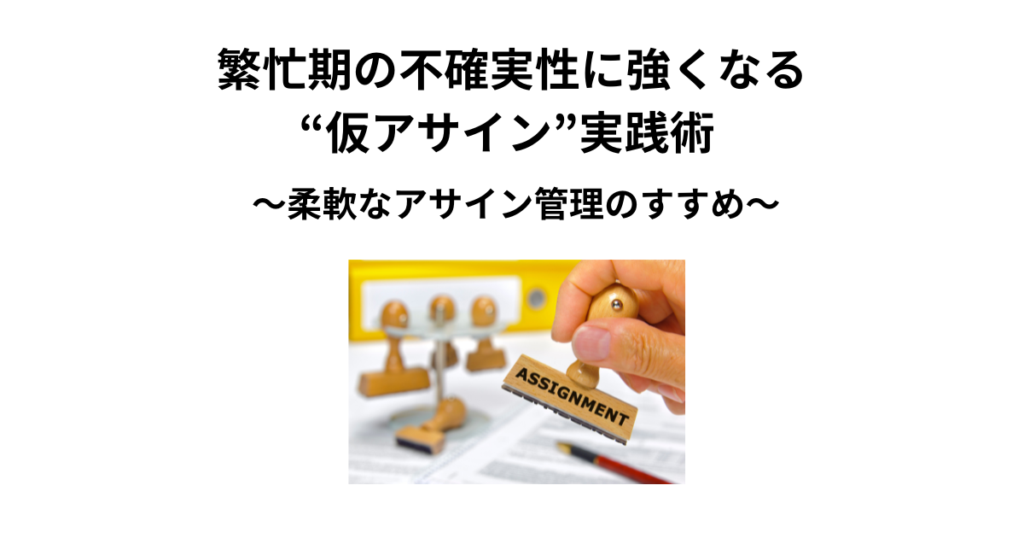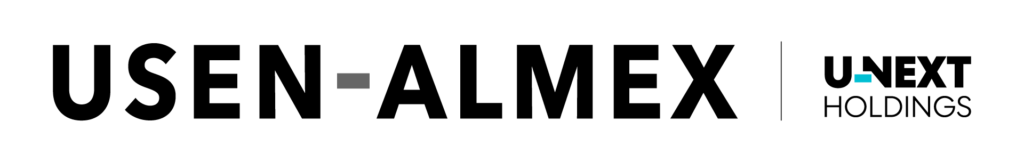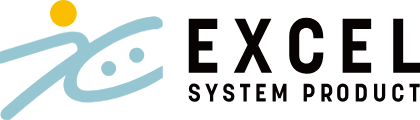アサイン管理と経営戦略の統合 — リソース計画を経営視点で考える
事業戦略を描いても、実行段階で「必要な人材が足りない」「特定部門に負荷が集中する」などの壁に直面しがちです。 多くの組織では、経営計画と現場のアサイン計画が別々に運用され、その“すき間”で不整合が生じています。 アサイン管理は単なる「見える化」や「調整」の仕組みではなく、 経営戦略を実行に落とし込む橋渡し機能です。 本記事では、リソース計画を事業戦略/経営戦略と統合するポイントを解説します。
アサイン管理を事業戦略・経営戦略とつなげる意味
戦略実行で生じる“リソース計画のギャップ”
- 新規事業を立ち上げたいのに必要人材が確保できない
- 成長領域に人を割けず、既存業務に埋没してしまう
- 案件の増減に合わせた柔軟な人員再配置ができない
背景には、戦略とリソース計画の分断があります。
アサイン管理が経営戦略の実行を支える理由
アサイン管理は、単なる人員配置ではなく、 経営資源の配分を最適化し、事業戦略を現場で実行する仕組みです。 リソース計画を戦略と結びつけることで、戦略は「現場の動き」へとブレイクダウンされます。
経営視点で考えるリソース計画とアサイン管理のポイント
長期的な事業戦略に基づくリソースプランニング
経営戦略が3年スパンでも、人材確保が後追いでは実行が遅れます。 事業戦略から逆算したリソース計画により、採用・育成のタイミングを前倒しし、必要人材を適切に配置できます。
株式会社NTTデータNJKでは、従来Excelでアサイン管理を行っており、調整に多大な工数が発生していました。 Co-Assign導入後は「アサイン会議が不要」になるレベルの運営を実現し、戦略に基づく大枠配置と現場の短期調整が大幅に効率化されました。
短期のプロジェクト調整と経営戦略の二層構造
- 長期:経営戦略に基づく重点領域の人材配置
- 短期:週次・月次のアサイン調整(案件増減やメンバー状況に即応)
二層を組み合わせることで、安定性と柔軟性を両立できます。
シナリオ比較で最適な人材配置を経営判断に活かす
「案件Aを優先すると営業リソースが不足」「案件Bを後ろ倒しで技術部門に余力」など、複数シナリオを比較することで、 戦略とリソースの最適解を経営層が選びやすくなります。
戦略余力(Strategic Slack)の設計 — リソース最適化の新常識
常時100%稼働のリスクと経営資源の柔軟性
「常に全員を100%稼働させる」ことは一見効率的に見えますが、突発案件や方針転換に対応できず、組織の柔軟性を奪います。 さらに、メンバーの疲弊や離職リスクも高まります。
戦略的余力の設計
10〜15%の余力を意図的に確保することで、新規施策や緊急対応に迅速にリソースを投下できます。 この余力は「遊休」ではなく、経営戦略を支える投資枠と捉えるべきです。
ペタビット株式会社では、Co-Assign によってプロジェクト損益の把握スピードが導入前に比べて15倍以上改善しました。 予実管理がリアルタイム化されたことで、余力を持ちながらも迅速に経営判断が下せる体制を構築しています。 導入事例はこちら
ツールで実現する戦略的リソース管理
- 誰が、いつ、どの程度余力を持つのかを把握
- 部門をまたいだ人材再配置が容易に
- 経営戦略に基づく「戦略余力」の確保が可能に
ツールを活用することで、リソース計画と事業戦略の統合が現実のものとなります。
まとめ — アサイン管理は経営戦略を実行に移す仕組み
- アサイン管理は経営戦略/事業戦略の実行を支えるリソース計画の中核
- 長期プラン+短期調整の二層構造で、柔軟かつ安定したリソース最適化を実現
- 戦略余力を設計し、不確実性に強い機動的な組織運営へ
例:キリンビバレッジでは、Co-Assignによる可視化で 「いつなら対応可能か」を客観的に判断できるようになり、部門横断の調整がスムーズに。 関連記事(note)